発表
Announcement
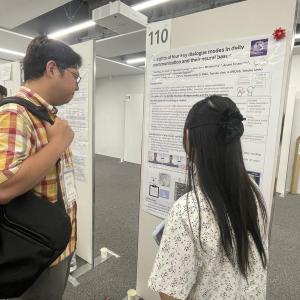
202509.07
日常コミュニケーションにおける4つの主要対話モードの洞察とその神経基盤(ポスター発表)
私たちは、日常的な会話を動機づける社会的モチベーションに基づき「Dialogue Modes(DM)」を定義しました。fMRIを用いた解析により、Relief、Comfort、Novelty、Hobbyモードがそれぞれ異なる神経的特徴を示す

202509.07
性格特性と楽観主義が実験的疼痛に与える影響:fMRI研究(ポスター発表)
性格特性が疼痛に影響を及ぼすことは多くの研究で示唆されています。 たとえば、外向性や協調性が高い人ほど疼痛耐性が高いとする報告がある一方で、協調性が高い人は社会的要請へのプレッシャーを受けやすく、かえって疼痛を我慢しにくいという指摘もあり
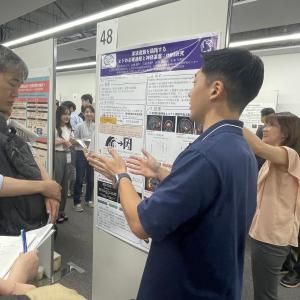
202509.07
津波避難を躊躇するヒトの心理過程と神経基盤:fMRI研究(ポスター発表)
これまでの研究で、津波即時避難には感情制御特性が寄与することが発見されていました。しかしながら、この感情制御特性がどのように津波即時避難に寄与しているのか、なぜ「即時的な」避難意思決定に寄与できるのか、どのような脳活動によって実現されている
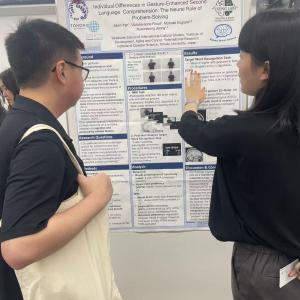
202509.05
第二言語記憶におけるジェスチャー効果の個人差:問題解決を支える脳の関与(ポスター発表)
第二言語(L2)における理解および記憶に対するジェスチャーの効果は、個人によって異なることが明らかになってきています。今回の日本心理学会第89回大会では、「第二言語記憶におけるジェスチャー効果の個人差:問題解決を支える脳の関与」というタイト
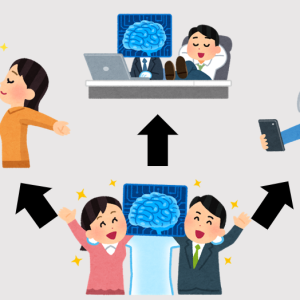
202509.04
AI支援の利用傾向の分類と比較(口頭発表:研究提案)
人工知能(AI)が広く普及している現代で、AIに対し依存的・補完的・反発的等、様々な利用方法が考えられますが、この分類と、グループ間で何が違うのかは明らかになっていません。本研究では感情的な意思決定を扱い、AI支援の有無により変動する脳活動

202509.04
どんな要素が音楽を聴いた時に私たちを「ノリノリ」にさせるのか? (口頭発表:研究提案)
私たちは、音楽を聴いた時にノリノリになって興奮したり体を動かしたくなることがあると思います。この感覚は「グルーヴ感」と呼ばれており、この喚起には最適な予測誤差が重要な役割を果たすことが先行研究で明らかになっています。しかしながら、どのような

202509.04
fMRIで探る:性格特性と楽観性が痛覚反応を変えるメカニズム (口頭発表・受賞)Posted in
私たちは、疼痛感受性の個人差をより多角的に捉えるため、心理尺度による評価と脳機能計測を組み合わせ、実験的疼痛に対する反応を検討しました。本研究の特徴は、行動実験とfMRI解析を併用し、心理的要因と神経基盤との対応を探索的に明らかにしようとし
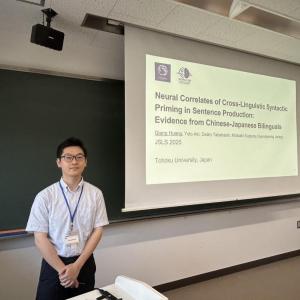
202507.13
バイリンガルはL1とL2で同じ統語処理システムを共有しているのか?(国際学会口頭発表)
バイリンガルがL1(第一言語)とL2(第二言語)の文を産出する際、統語的な情報はどのように統合されているのでしょうか。この統合的な処理は、単に表面的な語順の類似性に基づくものなのか、それともより深層的な抽象的統語表現に基づくものなのでしょう

202507.13
ジェスチャーはどのように第二言語習得を促進するのか:神経科学的視点から(国際学会口頭発表)
人は日常的にジェスチャーを使っています。それはあまりに自然で、しかしながら不可欠なコミュニケーション手段です。母語における共発話ジェスチャーの研究はかなり以前から行われてきましたが、第二言語(L2)の習得や理解におけるジェスチャーの役割に注
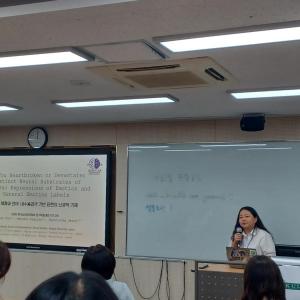
202507.04
感情の身体化と言語:内部受容感覚基盤表現の神経的メカニズム(口頭発表・受賞)
本研究では、「心がバラバラになった」のような身体内部の感覚に基づく特異的な感情表現が、より一般的な感情表現と比べて脳内でどのように処理されるのかを、機能的磁気共鳴画像法(fMRI)を用いて測定し、言語と身体感覚がどのように連携して感情体験を

